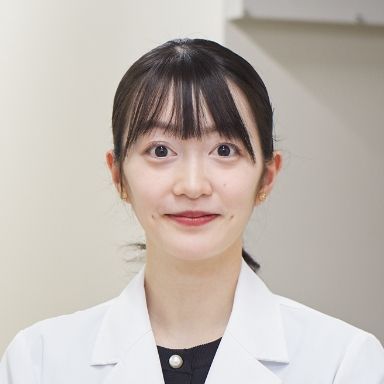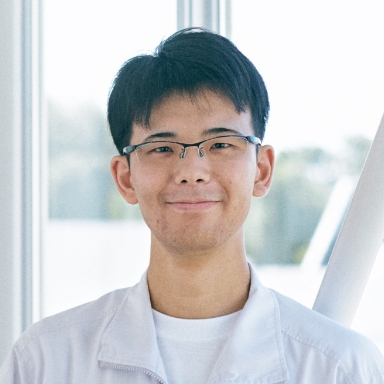開発職
候補化合物の特徴を最大限に引き出し、早く患者さんに届けるための開発戦略・開発計画を立案の上、それに基づいた臨床試験(治験)の計画を策定し、試験を実施します。臨床試験で得られたデータから、有効性・安全性を評価・検証し、当局への申請資料を作成するという医薬品開発の最終部分を担っています。特に皮膚科領域において前例のない治験を行うことも多いため、治験の評価方法を検討するところから取り組むこともあります。
※当社では治験への新たな取り組みも進めており、詳細はこちらをご参照ください
- CRA(Clinical Research Associate)
- 開発品の開発戦略を立案し、それに基づいた臨床試験の計画を策定します。試験実施時には実施施設を訪問し、モニタリング業務を行います。
- CQA(Clinical Quality Associate)
- 臨床試験で予想されるリスクを特定し、プロセス改善を行うことで試験品質を確保します。関連部署と連携し、治験薬の管理や承認申請対応を実施します。また外部委託先、標準業務手順書(SOP;Standard Operation Procedure)や教育の管理を担います。
- MW(Medical Writing)
- 臨床試験の実施に必要な治験薬概要書を作成します。また臨床試験終了時には治験総括報告書を作成します。承認申請時には承認申請資料(CTD;Common Technical Document)の作成に携わるとともに、臨床試験結果の論文を作成し、学術誌に投稿します。
- TR(Translational Research)
- 基礎研究の成果を臨床の場に橋渡しすることで、新しい治療法・診断法(バイオマーカー探索)の開発や臨床開発におけるPOC(Proof of Concept)の成功確度を高めるための臨床研究の計画を策定し、遂行します。
※臨床試験において実施される「DM(Data Management)」及び「統計解析」はデータサイエンス職をご参照ください。