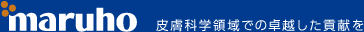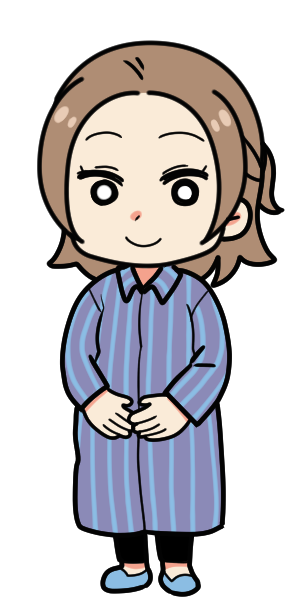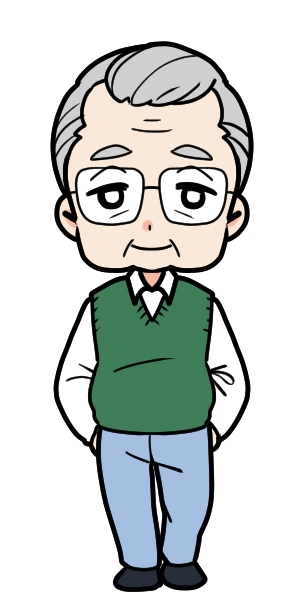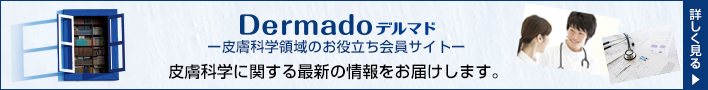- ホーム
- 痔の患者さんに効く、ポジティブトーク集
- 出産をきっかけに痔の症状が悪化した患者さん ポジティブトーク
痔の患者さんに効く、
ポジティブトーク集


出産をきっかけに痔の
症状が悪化した患者さん
- 育児に追われることにより睡眠不足やストレスをためることが多くなった。
- 授乳により脱水状態になる。
- これらの要因により便秘や痔を悪化させやすいため、薬剤師からアドバイス。

赤ん坊を連れている痔のお母さんか・・・もしかしたら出産をきっかけに痔が悪化したのかもしれないな・・・。
-

こちらのお薬を処方されるのは今回初めてですか?
それとも、他のクリニックでお薬を処方されたことはありますか? -

お薬を処方されるのは今回が初めてなんですが、症状は出産前からあってずっと悩んでいたんです。

-

そうなんですね。実は出産前から症状がある方も多くて、出産をきっかけに症状がひどくなる方もいらっしゃるんです。
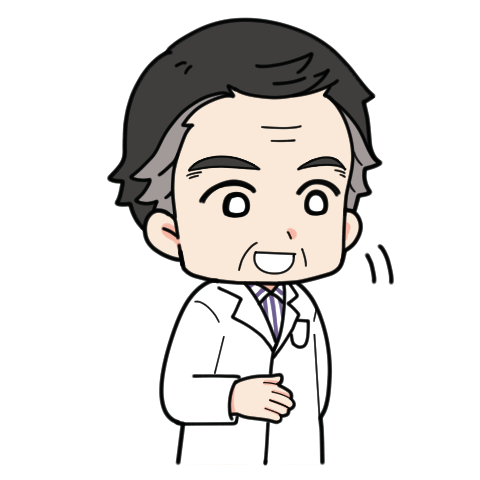
-

そうなんですか。私も出産してから特に症状がひどくなりまして・・・。
-

お薬をきちんと使うことはもちろん重要なんですが、出産後は育児のため生活習慣が大きく変わります。それが原因で症状を長引かせたり、悪化させてしまうこともあるんです。
![]()
このような場合は、以下の点について
アドバイスをしてみましょう。
育児による
睡眠不足やストレス授乳による脱水状態
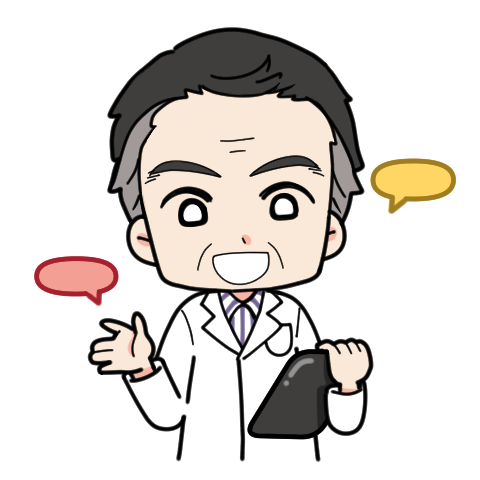

-

毎日育児で大変だと思いますが、睡眠は十分とれていますか?
-

出産後はあまり睡眠がとれない状態が続いています。夜中も子どもが泣き出して起こされたりで・・・。
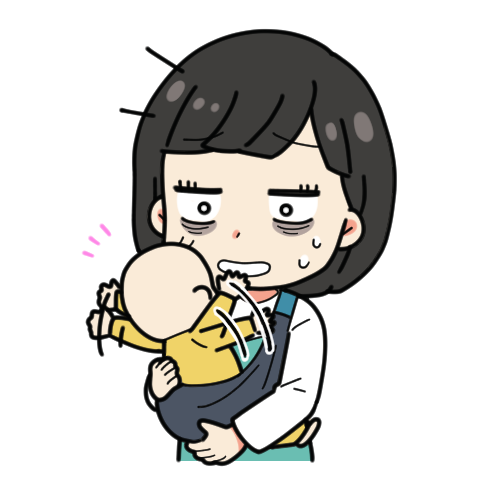
-

睡眠不足だったり、睡眠の途中で起きたりすることが多い方に便秘が多いといわれています。
ご家族にもう少し育児を分担するなどしてもらって、睡眠時間を確保することも大切ですよ。 -

そうですね、話し合ってみます。
-

ほかに悩んでいることはありませんか?
-

なかなか自分の時間がもてなくてイライラすることも多くなりました。
-

ストレスも便秘にはよくないんです。
難しいとは思いますが、ご家族や周囲の方に協力をしてもらい、時々はご自分の時間をつくって趣味を楽しむなど、気分転換をするようにしてください。 

-

授乳されている方は体の水分量が低下するため便が硬くなりやすいんです。便が硬くなると、痔の症状を長引かせたり、悪化させたりしてしまいます。
ですので、1日1.5~2Lくらいを目安に水分をとるようにしてください。 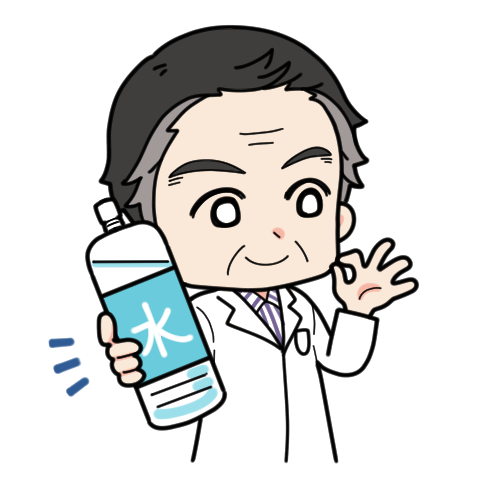
-

そうなんですか、授乳が便秘につながるんですか・・・。

-

体の水分量が低下すると、便秘以外の症状として、のどが渇くのはもちろんですが、頭がぼんやりする、食欲不振になる、イライラするなどの症状が出ることもありますので、そういった症状にも注意してください。
-

のどが渇くだけじゃないんですね。
-

今回処方された痔の外用薬は患部に直接作用するお薬なのですが、市販の便秘薬のような飲み薬の場合は、お薬の成分が血液を通じて母乳にも移行し、その母乳を飲んだ赤ちゃんが下痢になることもありますので、購入する際は必ず薬剤師に相談してください。
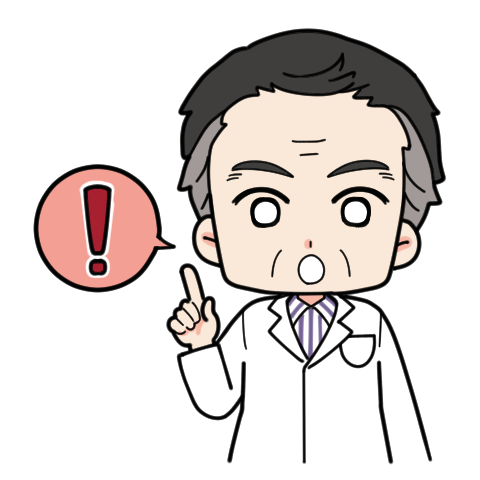
-

はい、お薬のことで気になることがあれば、事前に相談するようにします。

ワンポイント・アドバイス
出産後に便秘になる女性の割合
妊娠可能年齢の非妊娠女性では5人に1人が便秘であるのに対し、妊娠中期~後期では5人に2人、出産後早期には2人に1人以上が便秘を経験すると報告されており、妊娠中・出産後の女性は便秘になりやすいとされています1)。
睡眠やストレスと便秘の関係
睡眠と便秘の関係について、睡眠の質を評価したアテネ不眠尺度で6点以上の不眠者は便秘群で31.7%、非便秘群で16.4%と便秘群で多く、また中途覚醒時間も便秘群で長いことが報告されています2)。
<アテネ不眠尺度とは>
世界共通の自己評価不眠症判定法で、WHOが設立したプロジェクトが中心となって作成されたものです。8つの質問項目に対して4段階の回答があり(0~3点換算)、最大24点で数値化され、高得点であるほど不眠症の可能性が高いと判定されます3)。
また、ストレスが続くと交感神経が強く刺激されるため、腸の蠕動運動が抑制され、便秘につながりやすいとされています4)。
出産後の女性が便秘になる要因1)
- 水分摂取量の低下や授乳による脱水
- 出産後に食事が不規則になること
- 貧血への鉄剤の内服
- 会陰裂傷や帝王切開創部の疼痛への鎮痛剤の投与や硬膜外麻酔の影響 など
産褥期(出産後約6週間)に痔になりやすい理由
妊娠中の血液量の増加、プロゲステロンの産生増加、便秘傾向、増大した子宮による下大静脈など周囲血管への圧迫などにより肛門内部静脈叢がうっ血し、痔核ができやすい状態となっていることに加え、分娩時の努責、児頭による直腸、肛門部への圧迫などが重なるため発症します2)。
一般的に、出産直後の痔核は軽快しますが、痔核そのものが消失するわけではないため、出血や疼痛、違和感が長期に持続する場合は医療機関を受診するようにアドバイスしましょう3)。


- 森田 恵子, 月刊薬事 64(5), 920‐924, 2022
- 高野 正太, 日本大腸肛門病会誌 72(10), 621-627, 2019
- 湧井 宣行 他, 日本地域薬局薬学会誌 5(2), 38-44, 2017
- 岩矢 和子, 透析ケア 18(8), 755-758, 2012
- 森田 恵子, 月刊薬事 64(5), 920-924, 2022
- 末永 香緒里 他, 産婦人科治療 96(増刊), 793‐798, 2008
- 中尾 真大, ペリネイタルケア 夏季増刊, 216-219, 2020
![]()
この患者さんの別のトーク例
- 製品に関するお問い合わせ
-
フリーダイヤルがご利用いただけない場合06-6371-8898
※9時30分~17時30分(土日祝日及び当社休業日を除く)
-
インターネットはこちらから