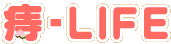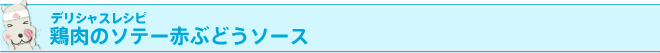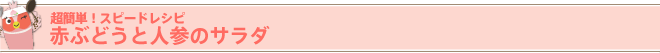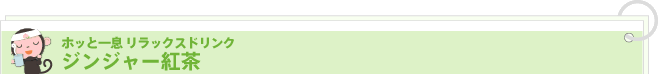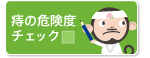赤ぶどう
赤ぶどうの果皮や果汁、種には、数種類のポリフェノールが含まれています。その中で特にレスベラトロールとプロアントシアニジンには血行を促し、うっ血を防ぐ働きがあると言われています。また、血管が酸化されてもろくなることを防ぐなどの抗酸化作用が強く、炎症を抑えるなどの働きもあると言われています。
ぶどうはそのまま食べることが多いですが、お料理にも活用してみましょう。皮は口に残って食べにくいものですが、ポリフェノールが多く含まれるので、ソースを作る際に皮を加えたりして無駄なく使う工夫をしましょう。
| ※ | ぶどうは果皮の色によって、赤・黒・青に分類されます。しかし一般的に、色素の多い赤ぶどうと黒ぶどうは「赤ぶどう」と呼ばれているため、表記もわかりやすいよう「赤ぶどう」としています。 |
赤ぶどうの酸味とバルサミコ酢のコクが鶏肉の旨味を引き立てます。

| 栄養価(1人分) | |
| カロリー | 308.7kcal |
| 食物繊維 | 0.6g |
| タンパク質 | 17.2g |
材料2人分
| 鶏もも肉 | 200g |
| 赤ぶどう | 8粒(100g) |
| ニンニク(スライス) | 1/2片分 |
| 塩(鶏もも肉下味用) | 適量 |
| コショウ | 適量 |
| 小麦粉 | 適量 |
| オリーブオイル | 大さじ1/2 |
| バルサミコ酢 | 大さじ1 |
| みりん | 大さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 粒マスタード | 小さじ1 |
| クレソン | 適量 |
作り方
- 赤ぶどうは皮をむいて種を除き、実を半分に割ります。皮も使うので、とっておきます。
- 鶏肉に塩・コショウをすり込み、軽く全体に小麦粉をふります。
- テフロン加工のフライパンにオリーブオイルとニンニク(スライス)を入れて弱火で温め、香りが出たらニンニク(スライス)を取り除き、鶏肉を皮から弱火でじっくりと焼きます。皮がこんがり、肉の中が6割ぐらいまで焼けたら裏に返して、弱火のままでさらに15分ほど火を通します。
- 3の鶏肉を取り出し、1の赤ぶどうの実と皮を入れて中火で炒めます。赤ぶどうから出た果汁が煮立ったらバルサミコ酢、みりんを入れて強火でかきまぜながら、とろみがつくまで水分をとばし、ぶどうの皮を取り除いて塩、マスタードを入れて混ぜ合わせます。
- 皿に鶏肉を盛りつけ、4のソースをかけてクレソンを添えます。

食材の使い方・ポイント
赤ぶどうの皮をとるのが面倒なときには、皮をむかずにそのまま調理して、皮がはじけるまで煮て食べてもよいでしょう。最近は皮ごと食べられる品種もあるので、そのような品種を利用すると無駄がありません。
赤ぶどうの甘酸っぱさが食欲を高めます。人参のシャキシャキ感がクセになるおいしさです。

| 栄養価(1人分) | |
| カロリー | 73.5kcal |
| 食物繊維 | 1.5g |
| β-カロテン | 4114.2μg |
材料2人分
| 赤ぶどう | 6粒(80g) |
| 人参 | 100g |
| 塩(人参の下味用) | 小さじ1/2 |
| 塩 | 少々 |
| 黒コショウ | 少々 |
| 酢 | 大さじ1 |
| オリーブオイル | 大さじ1/2 |
作り方
- 人参はせん切りにし、塩をふって少ししんなりしたら、洗って水をきります。
- 赤ぶどうはボールの中で皮や種を取り除き、半分に割ります。その際に出た赤ぶどうの果汁はとっておきます。
- 人参、2の赤ぶどうを混ぜ合わせ、塩、黒コショウ、酢、2の赤ぶどうの果汁を加えてよく混ぜ、オリーブオイルをまわしかけて混ぜ合わせます。
- 器に盛り、お好みでイタリアンパセリをちらしてもよいでしょう。

食材の使い方・ポイント
人参が苦手な人も多いですが、生で食べる方が人参独特のにおいは気になりません。ミネラルや食物繊維が多く含まれる干しぶどうを使ってもよいでしょう。
しょうがの辛味成分や紅茶には身体を温める作用があると言われています。少し気温が下がった日には、ジンジャー紅茶で身体を温めてリラックスしましょう。紅茶に含まれるファイトケミカルであるタンニンには、止血・消炎作用があります。

| 栄養価(1人分) | |
| カロリー | 2.6kcal |
| タンニン | 0.18mg |
材料2人分
| 紅茶葉 | 2g(ティースプーン2杯) |
| 熱湯 | 360cc |
| しょうが | 5g |
作り方
- お湯を沸騰させます。
- しょうがをすりおろします。
- 温めたティーポットに紅茶葉を入れてお湯を注ぎ、3~5分ほど蒸らします。
- 紅茶葉をこしてカップに注ぎ、2のしょうがのすりおろしを加えます。

食材の使い方・ポイント
しょうがの量はお好みですが、辛みが気になるときは、しょうがの搾り汁の量を調整しましょう。しょうがの辛み成分はショウガオールやジンゲロンというファイトケミカルの一種で、血行を促し、うっ血を防ぐ働きがあります。甘味が欲しいときは、はちみつを加えましょう。はちみつには善玉菌のエサとなるオリゴ糖が含まれ、腸内環境を整えるので便秘予防にもおすすめです。