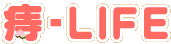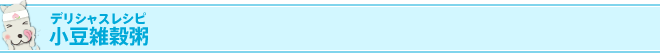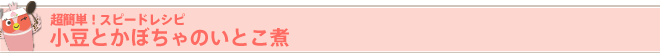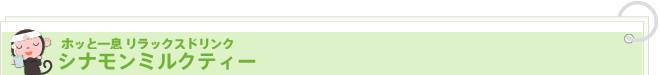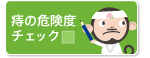小豆
小豆に含まれている主な成分は糖質やタンパク質ですが、ビタミンB1、B2、B6などのビタミンB群、カルシウム、リン、鉄分、亜鉛などのミネラルも豊富に含まれています。また、食物繊維も多く含まれているので、腸内環境を整えることにより便秘の予防や改善に役立ちます。このように栄養豊富な小豆は、古くから薬膳や民間療法でも使用されてきた食材です。特に、腫れ物を抑える薬として利用されてきましたが、こうした作用に関わる成分が実際に含まれていることが、近年解明されてきました。例えば小豆の皮の部分には炎症を鎮める作用があるサポニン(アクの成分)が多く含まれています。またサポニンには便を軟らかくする作用、血行を促す働きなどもあります。赤い色素成分であるアントシアニンにも血行を促す働きがあると言われています。このサポニンとアントシアニンはファイトケミカルの仲間です。
一般的に小豆は一度茹でこぼしてアク抜きをしますが、サポニンやアントシアニンなどの有効成分やビタミンB群などの水溶性ビタミンも減ってしまいますので、今回はアクをすくう程度にして茹で汁を使いました。
消化がよく栄養価も豊富で、お正月の食べすぎで疲れた胃腸を休めるのにぴったりのお粥です。

| 栄養価(1人分) | |
| カロリー | 163.9kcal |
| 食物繊維 | 2.3g |
| 鉄分 | 0.9mg |
材料2人分
| 小豆(乾燥) | 20g |
| 水 | 2カップ+100cc |
| 米 | 1/2合(うち雑穀を大さじ2ブレンド) |
| 水+小豆の茹で汁 | 3+1/2カップ |
| 塩 | 少々 |
| 三つ葉 | 少量 |
作り方
- 水洗いした小豆を鍋(あれば土鍋※1)に入れ、水2カップを加えて火にかけ、沸騰したら冷水100ccを加えて温度を下げます。再度沸騰したらふたをして、弱火で約30分ほどかけて少し硬めに茹で※2、ザルに上げます。茹で汁は捨てずにとっておきます。
- といで水をきった米と小豆の茹で汁、水を合わせて鍋(あれば土鍋)に入れ、強火にかけます。沸騰したら塩を加えてごく弱火にし、アクをすくいながら約40分、上澄みがひたひたになるまで煮込みます。
- 2を器に取り分け、刻んだ三つ葉をちらします。
| ※1 | 他の鍋でもかまいませんが、鉄鍋は鉄分がアントシアニンと結合して黒褐色に仕上がってしまうのであまりおすすめできません。 |
| ※2 | 1で小豆を茹でる際、鍋の大きさなどによっては、途中で水が減りすぎる場合があります。その場合は小豆がかぶるぐらいの水を加えて茹でます。 |

食材の使い方・ポイント
2で小豆のアクが出てくるので、丁寧にすくってください。
より簡単に作るには、市販の茹で小豆を使用するとよいでしょう。
また、お米に混ぜる雑穀は、色々な雑穀をブレンドしたものが市販されているので、利用すると便利です。
時間がかかる“いとこ煮”を市販の茹で小豆を使用して簡単に作りましょう。

| 栄養価(1人分) | |
| カロリー | 222.0kcal |
| 食物繊維 | 10.4g |
| 鉄分 | 1.6mg |
材料2人分
| かぼちゃ | 300g(約1/4個分) |
| 茹で小豆 | 70g |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| みりん | 大さじ1 |
| 濃口醤油 | 大さじ1 |
| ダシ | 1カップ |
作り方
- かぼちゃは種とわたを除いて一口大に切ります。
- 鍋にダシ、みりん、砂糖を入れて火にかけ、かぼちゃを加えて落としぶた※をし、中火で約10分、かぼちゃが軟らかくなるまで煮ます。
- 茹で小豆を加えて沸騰させ、濃口醤油を加えて煮汁が少なくなるまで煮ます。
| ※ | 落としぶたが無い場合は、アルミホイルやクッキングシートでも代用できます。 |

食材の使い方・ポイント
この料理は本来、乾燥小豆を先に軟らかくなるまで弱火で煮て、後からかぼちゃを加えます。時間差をつけて“追々”煮るので、「甥と甥=いとこ煮」と呼ばれます。
シナモンの辛み成分は血行を促すことで身体を温めます。また香りには気分を高める作用があると言われています。

| 栄養価(1人分) | |
| カロリー | 64.8kcal |
材料2人分
| 紅茶葉 | ティースプーン2杯(約6g) |
| シナモンスティック | 1本 |
| 水 | 180cc |
| 牛乳 | 180cc |
作り方
- 鍋に水を入れて沸騰させ、砕いたシナモンスティック※と茶葉を入れてから火を止め、ふたをして2~3分蒸らします。
- 1に牛乳を加えて沸騰しない程度に温め、茶こしでこしてカップに注ぎます。
| ※ | シナモンスティックが無ければ、シナモンパウダーで代用できます。その場合、シナモンパウダーの量はお好みで加減してください。 |

食材の使い方・ポイント
シナモンの揮発性の精油成分(芳香成分)が逃げないように、蒸らす間はふたをしておきましょう。
お好みで砂糖を加えてもよいでしょう。