褥瘡予防の栄養管理
- 総監修:
-
- 群馬大学 名誉教授 石川 治 先生
- 監修:
-
- 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック 安部 正敏 先生
- 訪問看護ステーション 有限会社きらくな家 代表 中里 貴江 先生
褥瘡管理と栄養の関係
褥瘡と栄養状態は密接な関係にあり、低栄養は褥瘡発生の危険因子であるとともにその治癒を妨げる因子にもなっています。したがって、褥瘡予防および治療には適切な栄養管理がきわめて重要といえます。
まずは患者さんの栄養状態の評価(アセスメント)を行い、予防に必要な栄養量を算出します。そのうえで栄養摂取の経路を確保し、必要な栄養素が確保できるようにしましょう。
栄養管理の方法
- 栄養アセスメント
栄養アセスメント(栄養状態の評価)とは、栄養状態を主観的あるいは客観的に把握し、その程度を判定することです。
評価方法には(1)主観的な評価法(主観的包括的栄養評価:subjective global assessment:SGAなど)と、(2)客観的な評価法があります。客観的な評価法には栄養指標(nutritional index)といわれる各種身体計測値や血液生化学的検査値などが用いられます。また人間に必要なエネルギーや各種栄養素が欠乏した状態を低栄養(protein energy malnutrition:PEM)といい、褥瘡発生のリスクが高まる傾向にあります。
低栄養には、エネルギーと蛋白質が欠乏したマラスムス(marasmus)型、エネルギーは十分だが蛋白質が欠乏したクワシオルコル(kwashiorkor)型、双方の中間型であるマラスムス・クワシオルコル型に大別されています。
主観的包括的栄養評価-SGA 記事/インライン画像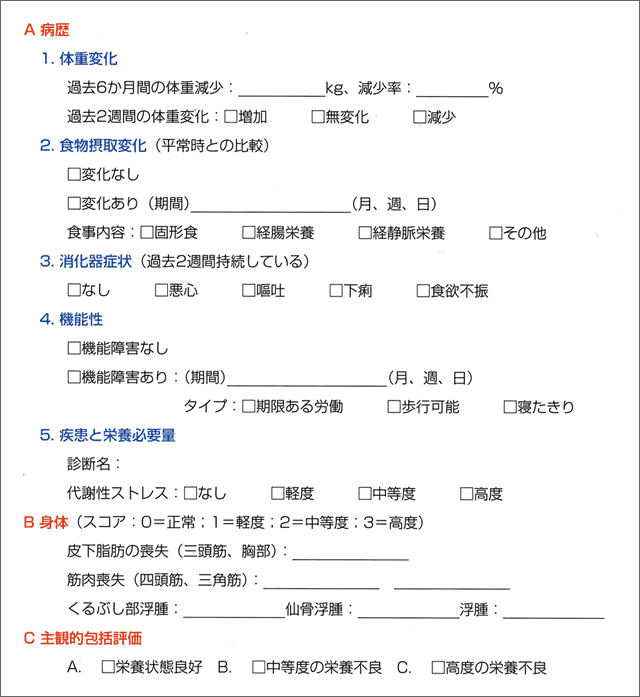
日本褥瘡学会編集:在宅褥瘡予防・治療ガイドブック:78, 2015
- 褥瘡予防に必要な栄養素と必要量
褥瘡発生を予防するためには、低栄養状態を改善するだけの必要栄養量の投与を行います。必要栄養量の算出は、一般的にはハリス・ベネディクトの式を用いるか、体重1kgあたり25~30kcal/日で求められます。また、創傷予防・治療の視点で検討した栄養素のはたらきと必要量の目安をまとめました。必要エネルギー量の計算式
〔ハリス・ベネディクトの式〕
基礎代謝エネルギー消費量(BEE)をまず算出する。
男性 BEE=66.47+[13.75×体重(kg)]+[5.0×身長(cm)]-[6.75×年齢]
女性 BEE=655.1+[9.56×体重(kg)]+[1.85×身長(cm)]-[4.68×年齢]
⇒必要エネルギー量の算出式
必要エネルギー量=BEE×活動係数×ストレス係数
- 活動係数
- 1.0~1.1 (寝たきり)
- 1.2 (ベッド上安静)
- 1.3 (ベッド以外での活動)
- 1.5 (やや低い)
- 1.7 (適度)
- 1.9 (高い)
- ストレス係数
- 手術:1.1(軽度)、1.2(中等度)、1.8(高度)
- 外傷:1.35(骨折)、1.6(頭部損傷でステロイド使用)
- 感染症:1.2(軽度)、1.5(中程度)
- 熱傷:1.5(体表面積の40%)、1.95(体表面積の100%)
- がん:1.1~1.3
- 体温:36℃から1℃上昇ごとに0.2増加
〔簡易式〕
- 現体重×30kcal
- 標準体重(身長×身長<m>×22)に25~30kcalを乗じて求める。
褥瘡治療・予防に関わる栄養素と必要量 栄養素 1日の必要量 役割 多く含む食品 エネルギー 予防:25~30kcal/kg
治療:30~40kcal/kg体蛋白の異化(分解)を防止 砂糖、穀類、芋類など 蛋白質 1.5~2.0g/kg 細胞増殖・コラーゲンなどの生成 肉類、魚類、卵、乳製品など ビタミンA 2000IU コラーゲンの合成・上皮の形成 レバー、うなぎ、緑黄色野菜など ビタミンC 褥瘡治療時150~500mg コラーゲンの合成 柑橘類、苺、ブロッコリー、緑茶など カルシウム
(Ca)600mg 細胞の増殖・代謝機能の維持 乳製品、小魚、木綿豆腐など 鉄(Fe) 15mg コラーゲンやヘモグロビンの合成 レバー、小松菜、海苔など 亜鉛(Zn) 15mg 細胞機能の維持 牡蠣、レバー、うなぎ、そら豆など 銅(Cu) 1.3~2.5mg コラーゲンの合成 レバー、すじこ、ココアなど 水分 25mL/kg/日
*発熱、尿量により異なる。生理機能を支える
*過剰摂取は皮膚の耐久性を低下させる。石川治:病棟・在宅での褥瘡対策ハンドブック:61, 2005より一部改変
- 活動係数
栄養管理の実際
- 栄養投与の進め方(経路)
栄養投与方法とは栄養を投与する経路のことを指し、経口、経腸、経静脈に大別されます。基本的には経口摂取が第一選択となりますが、嚥下状態や基礎疾患なども十分に考慮した上で行います。経口摂取が困難な場合は、消化管に問題がなければ経腸栄養を選択します。経腸栄養には経鼻胃管、胃瘻、腸瘻などのルートがありますが、患者の状態や介護者のニーズに合った方法を選択します。
また、投与経路の選択にあたっては、その状態がどの程度の期間継続するかも考慮することが必要です。 - 栄養補給
通常の食事のみでは栄養摂取が不十分な場合は、牛乳やヨーグルトなどの乳製品、プリン、ゼリーなど糖分の多い食品を副食として加えるか、栄養補助食品(サプリメント、高蛋白質食品、濃厚流動食品など)を用いる方法もあります。 - 自助具の活用
食事を自力摂取できる患者の場合、グリップを握りやすくしたスプーンやフォーク、傾斜をつけて食物をすくいやすくした皿など、工夫が施された自助具を活用すると食事に対する意欲がわき、食事摂取量が増えることもあります。食事用自助具の例 記事/インライン画像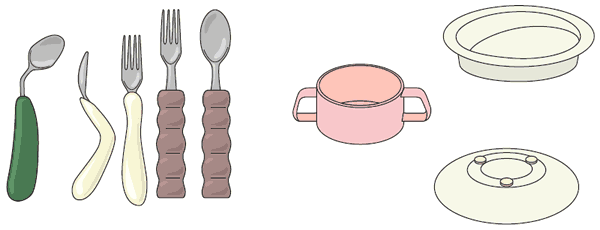
口腔ケア
高齢者では歯と歯の隙間が拡大し、それに伴う虫歯や歯周病、歯牙の欠損などが生じやすくなります。また、唾液分泌が減少し、口腔内乾燥による咀嚼障害、更に意識障害などがある患者では誤嚥性肺炎もしばしば発生します。誤嚥性肺炎は褥瘡悪化の引き金にもなるため、それを防ぎ、全身状態を少しでも良好に保つためには口腔ケアも大切な要素となります。
- 食前および食後、歯の隙間や口腔前庭部の食物の残りかす、歯垢・歯石などの除去を目標とします。
- 坐位あるいはそれに近い体位で行うことが望ましいですが、できない場合は麻痺側を上にして身体を横向きにさせて、誤嚥を防ぎます。
- 口腔内清掃には柄付きスポンジや歯ブラシの使用が最も望ましいですが、行えない場合は綿棒やガーゼを利用して口腔洗浄剤による清拭を行います。歯と歯の間の清掃には歯間ブラシを使用します。
- 意識障害のある患者では舌圧子などを用いて開口させてから、綿棒や巻綿子に含嗽剤をつけて口腔内を拭きます。口腔内を洗浄するときは水を少量ずつ入れ、吸引器で吸い取りながら洗います。



