がん性皮膚潰瘍マネジメントの現場から-施設インタビュー-:CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第3回:薬剤師の目線から
患者さんや家族のQOL向上を目指し
皮膚悪性腫瘍の治療に取り組むとともに
がん性皮膚潰瘍に伴う臭い等の症状にもしっかり対応
施設データ
- 診療科・部門
- 皮膚腫瘍科
- チーム体制
- 皮膚科医、皮膚腫瘍科外来看護師、各科病棟看護師、薬剤師など
- 専従スタッフ
- なし
-
記事/インライン画像
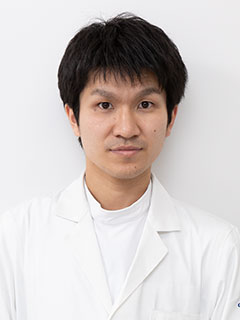
-
道家 由行 氏
国立がん研究センター中央病院 薬剤部【略歴】
国立がん研究センター中央病院で脳脊髄腫瘍科、皮膚腫瘍科を担当。
日本医療薬学会 がん専門薬剤師、日本病院薬剤師会 がん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療認定薬剤師
国立がん研究センター中央病院における薬剤師の体制
国立がん研究センター中央病院では、どのような体制で薬剤管理指導業務を行われていますか。
当院での薬剤管理指導業務は診療科担当と病棟担当に分かれて行っています。2つの担当は併任されており、原則、診療科担当が病棟担当を兼任するようにしています。例えば、乳腺・腫瘍内科の診療科担当は乳腺・腫瘍内科の病棟担当です。しかし、一部例外で診療科担当とは別の診療科の病棟を担当している薬剤師もおり、私は皮膚腫瘍科、脳脊髄腫瘍科の診療科担当と呼吸器内科、食道外科、頭頸部外科の病棟担当をしています(取材当時)。また、全診療科の経口抗がん剤のみで治療をされている外来患者さんを対象にした薬剤師外来も担当しています。
診療科担当は入院患者さん、外来患者さんの薬剤管理指導業務を担っています。入院、外来いずれにおいても、化学療法の初回導入時や継続中、化学療法の副作用による緊急入院といったところで薬剤管理指導を行っています。
外来患者さんの薬剤管理指導業務は、通院治療センターで行っています。マンパワーの関係から皮膚腫瘍科で治療を受けている患者さん全員に関与することは難しいため、前日に介入が必要な患者さんをピックアップし、当日、通院治療センターで患者さんが点滴中に薬剤管理指導や服薬指導を行います。
なお、診療科担当の薬剤師が担いきれない薬剤管理指導や服薬指導は、入院患者さんについては当該病棟の担当薬剤師が、外来患者さんについては通院治療センター担当の薬剤師がサポートしています。
がん性皮膚潰瘍ケアにおける薬剤師の役割
がん性皮膚潰瘍ケアに薬剤師はどのように関わっていますか。
がん性皮膚潰瘍ケアに関して、当院は基本的に皮膚腫瘍科や乳腺外科、乳腺・腫瘍科の医師と看護師が中心になって行っています。皮膚腫瘍科担当の薬剤師として、私ががん性皮膚潰瘍ケアで患者さんと直接関わるのは、ロゼックスゲルをはじめとした外用薬が新たに処方された時の薬の説明(作用機序、有効性、安全性、使用方法など)と、薬剤師外来です。ケアにおいての関わりとしては、医師や看護師の薬剤アドバイザーとしての立ち位置の方が大きく、外用薬の使用法や使用量について相談を受けることも多いです。
特に外用薬の使用量については少なすぎると十分な効果が得られず、多すぎると副作用のリスクがあります。医師や看護師と一緒に患者さん個々に適切な使用量を検討しています。皮膚腫瘍科の朝の回診時に週3回程度参加して、実際に行われている処置の方法や患者さんの情報を集めることもありますし、処方されている薬剤に関する理解度の低い患者さんに退院までに追加で説明するなどもしています。
また、一般的に患者さんは「もったいない」という気持ちがあるのか、外用薬を少なめに使う傾向があります。病棟や通院治療センター、薬剤師外来において、がん性皮膚潰瘍のある患者さんに関わった時には、患者さんに外用薬をどれぐらい使っているのか、処方された薬がどれぐらい残っているか、逆に薬がどれぐらい足りなかったかを確認するとともに、潰瘍の状態(臭いが強くなった、軽減したなど)などについての情報も得て、使用量の過不足について医師や看護師に報告しています。それとともに、例えば使用量が足りないと思われる患者さんには、「いついつまでに、何本使ってください」などと指導しています。患者さんの状態によっては、1日にロゼックスゲルが何本も必要になる場合もあり、薬剤師は院内におけるロゼックスゲルの使用量の把握と在庫管理もしています。
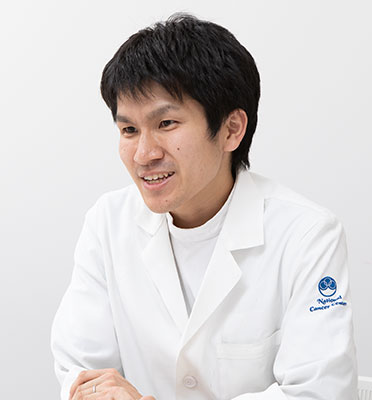
抗がん剤治療を受けられる患者さんの中で、医師が必要と判断された方については、初回診療後に薬剤師外来で処方された薬剤について説明しています。再診以降は、原則、医師の診察前に薬剤師外来を行うことになっています。患者さんの中には、医師に悩みや不安などを言い出せない方もおられますので、そうした悩みや不安などを伝えられた場合は、患者さんと一緒に解決策を考えることもあります。そのような中で、がん性皮膚潰瘍の臭いについて悩まれていることが分かれば、カルテ上で医師に患者さんの思いとともに、ロゼックスゲルの使用を提案することもあります。
外来患者さんはほとんどが院外処方だと思いますが、薬薬連携はどのようにされていますか。
診療科担当の薬剤師が退院時指導の際に患者さんに薬の説明を行った上で、その内容について、メモやお薬手帳など何かしらの方法を介して患者さんから保険薬局薬剤師に伝えていただくようにお願いしています。がん性皮膚潰瘍のある患者さんの場合には、ケアの方法や外用薬の使用方法などについて、薬剤情報書の作成やお薬手帳などに書くようにしています。

このコンテンツは会員限定です。
マルホ会員に登録すると会員限定コンテンツをご覧いただけます。
- がん性皮膚潰瘍マネジメントの現場から-施設インタビュー-
-
- CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第1回:医師の目線から
- CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第2回:薬剤師の目線から
- CASE1.聖路加国際病院(東京都中央区) 第3回:看護師の目線から
- CASE2.昭和大学病院ブレストセンター(東京都品川区) 第1回:医師の目線から
- CASE2.昭和大学病院ブレストセンター(東京都品川区) 第2回:看護師の目線から
- CASE3.江南厚生病院緩和ケア病棟(愛知県江南市) 第1回:医師の目線から
- CASE3.江南厚生病院緩和ケア病棟(愛知県江南市) 第2回:看護師の目線から
- CASE3.江南厚生病院緩和ケア病棟(愛知県江南市) 第3回:看護師の目線から
- CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第1回:医師の目線から
- CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第2回:看護師の目線から
- CASE4.国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科(東京都中央区) 第3回:薬剤師の目線から



