maruho square 皮膚科クリニックの在宅医療奮闘記:しくじり話
-
- 小川皮フ科医院 院長 小川 純己 先生
今回は在宅皮膚科の訪問診療のしくじり話をお届けします。日常診療は試行錯誤の連続ですが、訪問診療ならではの「しくじり話」を選んでみました。
第壱話:訪問してみたら・・・
以前にも、訪問してみたら患者さんのお通夜の準備をしていた話をしました。居宅での通夜だったので遠目からもいつもと違う雰囲気があり、家族にお声かけする前から敗北感がありました。訪問前の再確認が重要だという教訓でした。午前の診察が押している場合は、ときに訪問前の再確認ができないことがあります。皮膚科への訪問診療の依頼は全身状況が悪くなってからのこともあり、急変は想定しておく必要があります。
今回の患者さんは膀胱癌のターミナルケアで、紅皮症のコントロール目的に訪問診療を行っていました。環境整備、清潔保持、外用の徹底で、ご本人のかゆみの訴えは改善傾向にあり、主治医からも皮膚症状の現状をご報告いただいた矢先でした。他科からの依頼による訪問診療は月1回のしばりがあるため、1カ月後に再診予定としていました。
いつも通り、玄関の呼び鈴を押すと、家族が出迎えてくれます。ご挨拶をすると、怪訝そうな表情で「ご連絡が行っていませんでしたか?」と言われ、やってしまった感満載の表情で平謝りの私。1週間前にご逝去され、一昨日には法事も終えられたとのことでした。ご臨終の様子を伺ってお宅を後にしました。
主治医ではないので、連絡が回ってこないのは仕方ないのですが、訪問看護師と一緒に動いていたら避けられたかもしれません。のけ者にされた感があるのは、ひがみ根性でしょうか。たっすいがー*はいかんですね。訪問前の再確認は重要です。
*土佐弁(朝ドラ「あんぱん」でご存じの方も多いかと思いますが):頼りない、男らしくない、弱々しいなど

第弐話:在宅のこだわり、そして・・・
在宅医療は、住み慣れた地域にある自宅で最期を迎えることを、患者さんの1つの理想とします。患者さんは身体能力の低下によって移動が難しく、医療機関への受診が困難になっています。在宅医療を行う中では、どの時点で病院受診をすすめるか、患者さんの希望とどう折り合いを付けるかが問題になります。
その患者さんは、元々循環器疾患で内科を受診されており、下腿潰瘍が生じたために、皮膚科の訪問診療導入となりました。身近な家族を亡くしたばかりで、その弔いのためにも永く自宅に居たいとのご希望でした。
環境整備、訪問看護導入、在宅で可能な外用治療および創部管理を続けました。もともと局所に循環障害があるため、下腿潰瘍の状態は一進一退でした。ある時期から潰瘍部に悪臭と多量の浸出を伴うようになり、二次感染が疑われました。発熱などの全身症状は明らかではないものの、疼痛が著明でした。抗生薬の内服を行うとともに、入院加療の必要性を説明しました。病院外来受診は承諾していただけましたが、入院治療は希望されませんでした。足浴の仕方、環境の再整備、疼痛管理などを行いましたが、潰瘍はますます大きくなり、患者さんの苦痛も徐々に増加していきました。ついには、疼痛のため室内で動けなくなり、救急車で搬送になりました。
入院後、下腿潰瘍に由来する敗血症と診断されました。救命のためには下肢切断が必須でしたが、外科的治療は希望されませんでした。家族の最期と自分の状態が重なったのでしょうか。主治医との間で治療方針と予後について十分議論をした上で、ご本人が覚悟したとおりの最期をお迎えになったと、主治医から丁寧な手紙をいただきました。
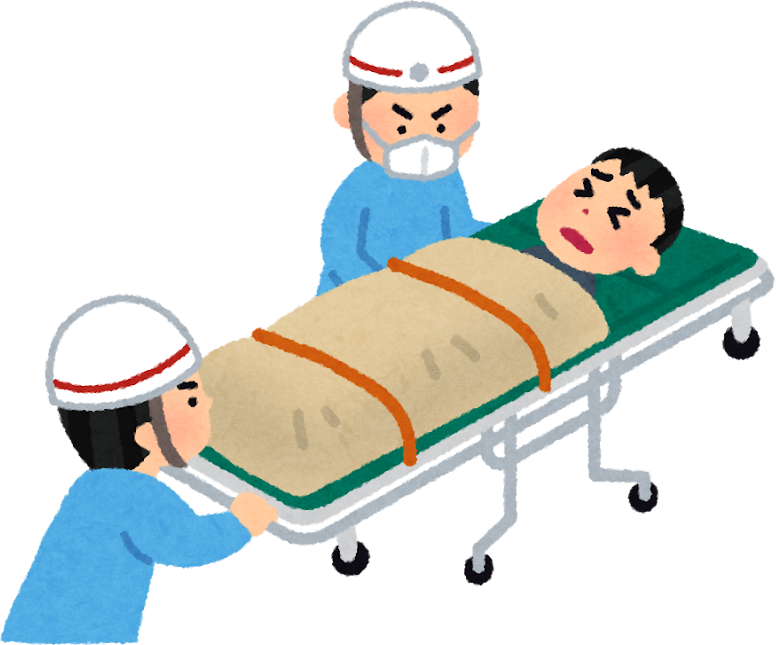
ご本人の生命にとっては、もっと早い段階での病院受診が良かったのかもしれません。しかしそれでは、ご本人が想定していた在宅医療とはかけ離れた生活を送ることになったかもしれません。あるいは、先に旅立った家族をじっくり弔う時間を得るために、何よりも命を優先した治療を実施するように根気よく説得するべきだったのかもしれません。
より良い選択肢が何だったのかが自分には分からない状態が、一番のしくじりだった気がします。
第参話:患者さんの話を傾聴するということ
皮膚科の訪問診療で話を聞く機会が多い相手は、患者さん、家族、訪問看護師です。使用しているデイサービスや訪問入浴サービスの利用法などはどうしても又聞きになります。
ある時、患者Aさんから、褥瘡があるためデイサービスで入浴できないと相談されました。一般細菌培養でも有意な菌は検出されず、創汚染か定着かという状態でした。良好な肉芽が形成されている赤色期だったので、創洗浄を積極的に行いたいところでした。施設の管理者に連絡して、「施設の感染マニュアルに従った順番、洗浄法で構わないので、入浴をお願いできないか」と相談してみました。何とか入浴は再開できたものの、Aさんからはその後も、入浴時間が短いとか、寒いとか、不満の弁が聞かれました。
全身状態の悪化から入退院を繰り返すと、徐々にAさんの認知症は進行し、周囲への不満はますますエスカレートしていきました。訪問看護師や日常の包帯交換を行う家族にもその矛先は向けられていきました。「自分の悪口を言っている」、「包帯交換時の段取りが悪い」とか、Aさんの訴えは留まることを知りませんでした。その頃は全身状態の悪化から一時的にデイサービスの利用や入浴が不可となっていたため、制限事項が不安定な精神状態に拍車をかけているのではと私は考えました。成功体験を1つでもしてもらうことを目的に、施設にAさんの入浴可能な時期について問い合わせてみました。
施設の担当者から聞かされた話は衝撃的でした。元気な頃のAさんは、デイサービスでお局的な存在で、命令的な口調で他の利用者に指示を出したり、電話番号を聞き出して、帰宅後も個人的に連絡を強要したりと、行動が施設内で問題視されていたというのです。医者からの環境整備についての提言も、Aさんがコネを使って圧力を加えているように捉えられているようでした。

そういえば、ケアマネジャーと衝突するので、担当者の変更をお願いしたという話を聞いたばかりでした。
問題行動が再開するかは不明でしたが、とりあえず施設には、通常の客観的な受け入れ可能な基準を教えてもらいました。医者から施設に物申すという行動がどれだけの意味を持つかを深く考えていなかったので、反省しきりでした。
環境整備は重要なことです。現在の病状における皮膚科的な見地を関係者に正しく伝えることは必須ですが、そこに何らかの損得勘定が絡んでくるとしたらどうでしょう。無自覚、無批判に患者さんの訴えを周りに伝えることは、本当に正しいことなのでしょうか。政治家がこれをやると、ポピュリズムのそしりを受けるかもしれません。公平が良いのか、平等が良いのかという話ではないかもしれませんが、行動指針の軸足を何処に置くべきか、途方に暮れました。
しくじりからの学びは、なかなか次につながりません。正解あるいは一般解は、そもそもないのかもしれません。個々の症例で、より良い方向性を、あるいは集合知でより多数が納得できる落とし所をみつけていくのがせいぜいなのでしょうか。
診療報酬に関しての小川皮フ科医院へのお問い合わせはご遠慮お願い致します。



