帯状疱疹と他疾患との併発における診断と治療:自己免疫疾患編<前編>
-
記事/インライン画像
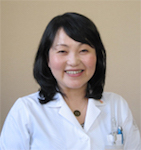
-
東京女子医科大学附属 膠原病リウマチ痛風センター
リウマチ膠原病内科 准講師
浦野 和子 先生施設紹介
リウマチ性疾患全般に対応する中心的施設として1982年に設立されました。外来患者数は一日約500名、一月では約1万名で、5,000名以上の関節リウマチ患者、多くの膠原病患者、痛風患者の診療を行っています。現在の医局員は所長以下67名。全国からリウマチ医を志す医師が集まっており、内科医と整形外科医が互いに協力して治療に当たっています。
自己免疫疾患(膠原病)
自己免疫疾患は、免疫システムのバランスが崩れ、自分自身の正常な細胞や組織を非自己と認識し攻撃を加えることから様々な症状をひきおこします。全身性自己免疫疾患の膠原病は、1942年に米国の病理医であるPaul Klempelerが提唱した疾患の概念です。
当時の疾病概念では、心臓、胃腸、肺、腎臓、肝臓など臓器別に病気を区別し診断・治療が行われていました。ところが、全身の膠原繊維に共通の異常が引き起こされ、臓器別の疾病概念では説明できない原因不明の多臓器疾患群が存在することがわかってきました。それらを1つの疾病概念として膠原病(コラーゲン病)と呼ぶように提唱したのが始まりです。彼が最初に膠原病と報告した疾患は6種類あり、関節リウマチ、リウマチ熱、全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎でした。現在では膠原病類縁疾患という概念があり、病態において自己免疫が関連し膠原病と同じくグルココルチコイドで治療することが多いが、他の膠原病を合併することが少ない、ベーチェット病、サルコイドーシス、脊椎関節炎などのことをいいます。表1に代表的な膠原病/膠原病類縁疾患を提示します。
| 関節リウマチ |
| 全身性エリテマトーデス |
| 多発性筋炎・皮膚筋炎 |
| シェーグレン症候群 |
| 混合性結合組織病(MCTD) |
| 血管炎症候群(高安動脈炎・側頭動脈炎・結節性多発動脈炎・ ウェゲナー肉芽腫・アレルギー性肉芽腫性血管炎・ Henoch-Shonlein紫斑病・ANCA関連血管炎) |
| リウマチ性多発筋痛症 |
| 抗リン脂質抗体症候群 |
| 成人発症Still病 |
| ベーチェット病 |
| サルコドーシス |
| 脊椎関節炎 |
このなかで関節リウマチの患者は圧倒的に多く、我が国では約60万人の患者さんがいるといわれています。特に女性に多く発症し、本邦での男女比は1対3~4と報告されています。
帯状疱疹の成因
帯状疱疹はいわゆるcommon diseaseで生涯罹患率は一般に10~30%といわれています。幼少時に水痘に罹患することで水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)に初感染します。VZVの感染力は強く、非免疫者が患者と接触した場合、90%以上が感染します。さらに、水痘が治癒した後も三叉神経節や脊髄後根神経節、坐骨神経節などにVZVは潜伏しつづけます。加齢やストレスなどによる免疫能の低下などをきっかけに再活性化されたVZVは神経線維束を障害しながら伝播し、神経の分布に沿って皮疹を形成し痛みを伴います。
膠原病患者における帯状疱疹の疫学
帯状疱疹はcommon diseaseであると同時に日和見感染症でもあります。白血病・悪性リンパ腫・肺がんなどの悪性腫瘍症例やその化学療法施行中の患者、HIV感染による後天性免疫不全症候群(AIDS)、骨髄疾患など免疫機能が低下している人では発生リスクが高く、重症化・遷延化しやすくなります(表2)。
| 促進因子 |
| Virus reactivation:液性免疫より細胞性免疫低下が強く関連する 加齢 悪性疾患:特に抗がん剤にて治療中の悪性リンパ腫・白血病・肺がんなど HIV陽性症例 自己免疫疾患 女性>男性 白人>黒人 Stressful event:精神的負荷により細胞性免疫低下 外傷:局所の後根神経節におけるvirus reactivation刺激が誘因となる IL-10遺伝子多型:-1028GA、-819CT、-529CA FinlandではATAハプロタイプ、韓国ではGCCハプロタイプが帯状疱疹発生リスクと 報告されており、人種差を認める |
| 抑制因子 |
| 病児と接する職業(小児科医や保育園勤務など) |
また、疫学調査では、膠原病患者は帯状疱疹の発症率が高いことが海外で報告されています(帯状疱疹発症率:全身性エリテマトーデス15~91人/千人・年、Wegeners肉芽腫45人/千人・年)※1。
2007年、Smittenらは米国と英国で帯状疱疹の千人・年あたりの発症率について解析した結果、非関節リウマチ群では、米国3.71、英国4.10に対して、関節リウマチ群ではそれぞれ9.83、10.60と、帯状疱疹の発症率が有意に高いことを報告しています(COX比例ハザードモデル米国HR1.94、95%信頼区間(CI):1.83-2.05、英国HR1.70、95%CI:1.61-1.79)※2。この理由のひとつとして、本邦に比し海外では関節リウマチの治療薬に生物学的製剤の使用割合やメトトレキサートの投与量が多いことが考えられます。
当センターでは、帯状疱疹発症の危険因子について2000年4月から2006年9月までの6.5年にわたり日本人関節リウマチの患者さんを対象とした前向きコホート研究※3を行いました。その結果、1,276名中103名に帯状疱疹の発症が確認されました。平均発症年齢は63.2±10.2歳で、55歳以上の患者さんの発症が高頻度でした(図1)。時間依存型ハザードモデルでの解析の結果、加齢・メトトレキサート内服は帯状疱疹発症が有意に高い危険因子でした(表3)※4。
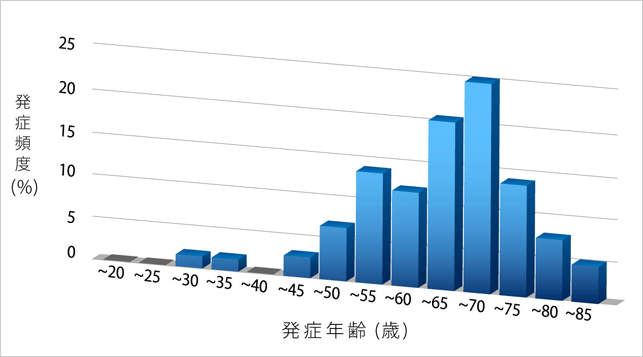
| Hazard ratio | P | |
|---|---|---|
| 女性 | 1.54 | 0.17 |
| 年齢(歳) | ||
| <45 45~59 60 ~74 75~ |
1 1.64 2.12 2.93 |
- 0.2 0.051 0.041 |
| J-HAQ*スコア | ||
| <0.25 0.25~0.99 1.00~ |
1 1.22 1.56 |
- 0.48 0.085 |
| CRP(mg/dl) | ||
| <0.2 0.2~0.5 0.6~1.4 1.5~ |
1 1.47 1 1.05 |
- 0.17 0.99 0.9 |
| 血沈(mm/h) | ||
| <20 20~31.9 32~50.4 50.5~ |
1 1.32 1.14 1.2 |
- 0.35 0.68 0.25 |
| Methotrexate内服 | 1.61 | 0.029 |
| Prednisolone内服>5mg/日 | 0.77 | 0.23 |
| IL-10 haplotype** | ||
| ATA ACC GCC |
1.41 0.78 1.27 |
0.38 0.21 0.45 |
| *J-HAQ:Japanese version of Health Assessment Questionnaire **IL-10遺伝子多型:-1082(A/G)、-819(T/C)、-592(A/C)で構成 |
||
我が国では生物学的製剤の使用例はまだ比較的少数(当センターでは通院中の関節リウマチの患者の約10%が使用)であり、メトトレキサートの平均投与量も少ないことから、欧米と比較すると発症率は低い可能性が考えられます。年々生物学的製剤の使用やメトトレキサートの使用量も増加しており、我が国でも関節リウマチの治療の進歩に伴い、今後更に関節リウマチ患者の帯状疱疹発症率は高くなることが予測されます。
膠原病患者の帯状疱疹
帯状疱疹は、一般に神経の分布に沿って皮疹を形成し痛みを伴うため、比較的診断しやすい疾患であるといえます。しかし、関節リウマチの患者などで水疱よりも痛みが先行して出現していると、線維筋痛症との鑑別が難しい場合も稀にあります。線維筋痛症の治療にはステロイド薬が使用され、帯状疱疹の治療とは異なります。経過観察を行い神経節に沿って皮疹が確認されたら帯状疱疹と診断し、すみやかに抗ヘルペスウイルス薬の投与を開始します。
(次回は、帯状疱疹の治療を中心に解説します。)
文献:
- HarpazR, et al. Advisory Committee on Immunization Practices(ACIP)Centers for Disease Control and Prevention(CDC).Prevention of herpes zoster : recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2008;57:1.
- Smitten AL,et al. The risk of herpes zoster in patients with rheumatoid arthritis in the United States and the United Kingdom. Arthritis Rheum 2007;57(8):1431.
- Matsuda Y, et al. Validation of a Japanese version of the Stanford Health Assessment Questionaire in 3,763 patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003; 49(6):784
- 浦野和子ら.帯状疱疹.リウマチ科 2009; 42(1):39-44
- 帯状疱疹と他疾患との併発における診断と治療
-
- 自己免疫疾患編<前編>
- 自己免疫疾患編<後編>
- 糖尿病編



